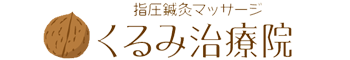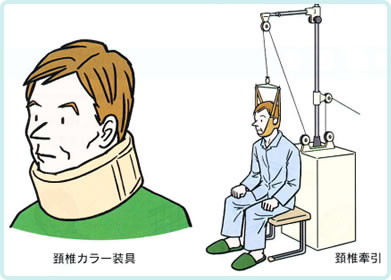秋冬季の養生法(1) ~玄(くろ)いものを食べよう~
カテゴリー:セルフケアと養生法
(※前回ブログ【「秋分」2017 】のつづきです)
「腎」を癒し、養うための生活習慣
――といってもいろいろありますが、
生命活動の基本である「飲食」の点から言えば、
「黒いものをお腹に入れる」
ということに尽きます。
「えっ? く、黒いものって何!?」
――そう思いますよね。
漢方医学は「陰陽論」と「五行学説」という
中国古代思想――当時の最先端思想――の
影響を受けながら発展してきました。
(※ →【陽きわまりて陰を生ず(2)】参照)
このうちの「五行学説」とは、
万物を五つの元素(=五つの特徴)に分類することで
相互間の関係を捉えようとする考え方のことです。
この五行学説に従って人体の生理機能を
解釈したものが「五蔵」の概念です。
つまり、人体の解剖・生理をも五つの特徴に分類し、
「肝, 心, 脾, 肺, 腎」の五蔵として捉え、
このうち「腎」には「冬」「黒」などを配当したのです。
(※ちなみに「肝=春・青」「心=夏・赤」
「脾=土用・黄」「肺=秋・白」が配当されています)

ここにいう「黒い」とは、必ずしも厳密な意味での
「ブラック」の色を表しているわけではありません。
飲食に関して言えば、筆者はこれを
「濃い茶褐色(の飲食物)」
を指していると解釈しています。
たとえば、紅茶やほうじ茶、味噌、
チーズ、玄米などがそうです。
色の淡い煎茶に比べれば、
紅茶やほうじ茶は明らかに濃い茶褐色ですし、
味噌やチーズは、それぞれ大豆・牛乳という
もともと白っぽい原料から比べると、
色がずいぶんと濃くなっています。
玄米も同様に、精製された白米と比較して
明らかに茶褐色をしているのがわかります。
「玄人」と書いて「くろうと」と読むように、
そもそも「玄」の字には
「黒い色」「濃い色」という意味があり、
玄米はかつて「黒米(くろごめ)」
とも呼ばれていました。
――以上、食材のごく一部ではありますが、
上に挙げたような飲食物を摂取することが
「腎」を養うことになるというわけです。
では、淡白なものと色の濃いものとでは
いったい何が違っているのでしょうか。
次回、詳しくお話ししたいと思います。
(※【秋冬季の養生法(2)】へつづきます)
**************************************************
奈良の鍼灸マッサージなら、指圧鍼灸マッサージ くるみ治療院
にお越しください。奈良市のしもみかど商店街の中にあります。
〒630-8365
奈良県奈良市下御門町17-1
TEL:0742-93-9600
受付時間:10:30~19:00
定休日:火・金(祝日営業)